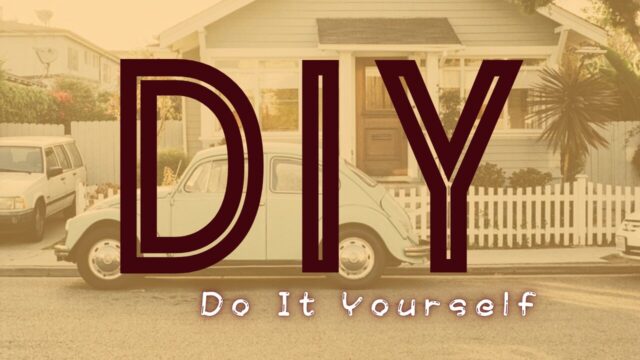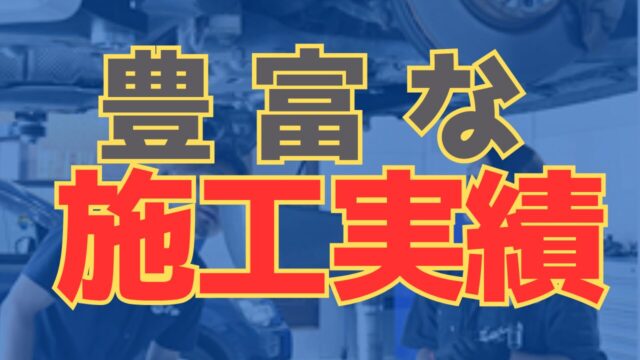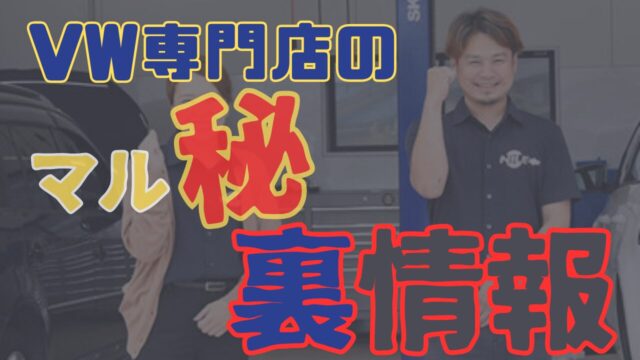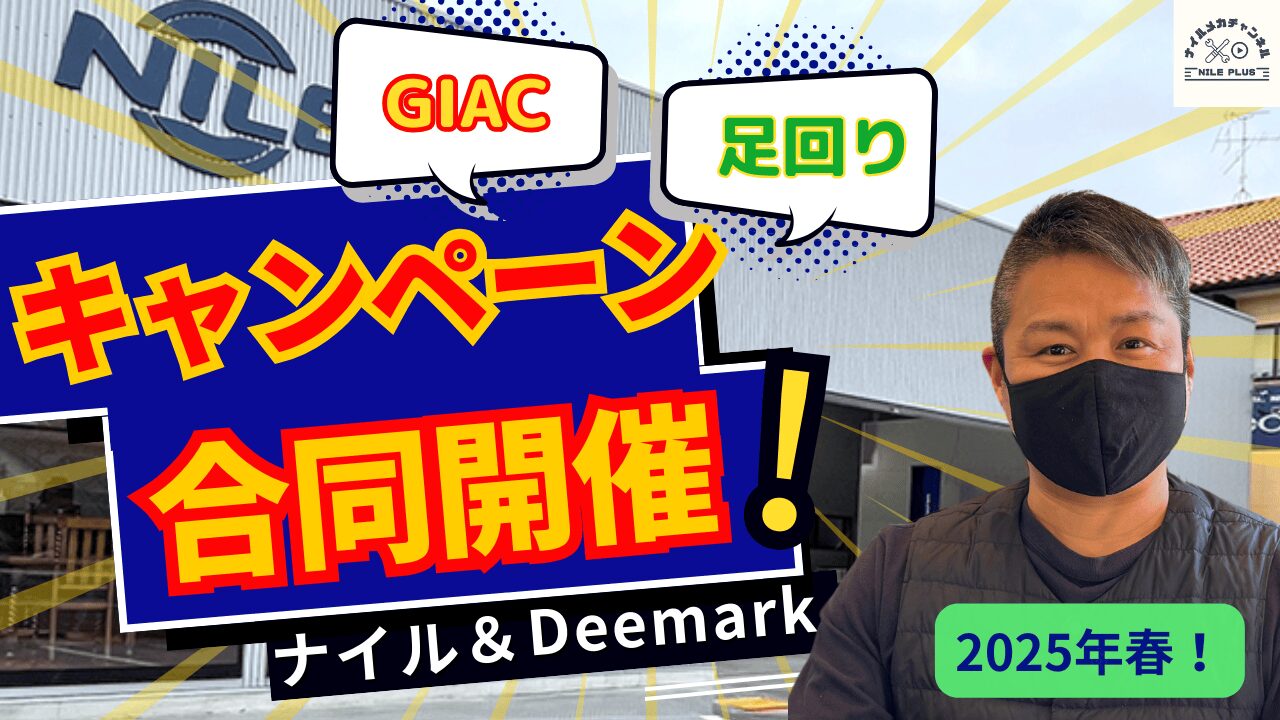みなさんこんにちは!ナイルの平田です!
今回はジャダーがひどいといういうことで、7速乾式DSGのクラッチ交換をしていきます!
参考動画:ナイルメカチャンネル「乾式7速DSGクラッチ交換」
関連記事:乾式7速DSG(DQ200)クラッチの構造と交換費用|ジャダー症状と長持ちのコツ
7速乾式DSGクラッチの“ジャダー”対策と交換作業まるわかり!
フォルクスワーゲン(VW)車などで採用されている「7速乾式DSG」は、軽快な変速と燃費性能を両立した優れものです。しかし、走行距離が伸びると“ジャダー(振動)”が気になり始めることも…。
ここでは 7速乾式DSGの仕組み や クラッチの構造・交換のポイント、そして ジャダーを抑えるコツ などを分かりやすく解説します。
1. そもそも「7速乾式DSG」とは?
● DSG(デュアルクラッチ・ギアボックス)の基本構造
- DSG = マニュアルトランスミッション(MT)をベースに、クラッチ操作・シフト操作を自動化した構造。
- 乾式DSG(DQ200)と湿式DSG(DQ250/DQ500など)があり、小排気量向けに採用されるのが7速乾式(DQ200)。
- 大きめの排気量・高トルクには湿式DSGを使うケースが多い。
● 乾式と湿式の違い
- 乾式:クラッチがオイルに浸っていない(空気中に露出)。軽量・コンパクトで、小排気量車への採用が中心。
- 湿式:クラッチがオイルに浸っている。オイル冷却で高トルクにも耐えやすいが、構造は大きく重くなる。
2. ジャダーの原因は“クラッチの消耗”が大半
● ジャダーとは?
- 発進や低速時、クルマ全体がガタガタと振動する現象のこと。
- DSGでよくある症状として「ジャダー=故障?」と不安になる方は多い。
● スパークプラグなどの点火系で改善するケースもあるが…
- 稀にプラグ交換で振動が軽減する例もあります。
- しかし、約8〜9割はクラッチ周りの問題が大きいのが現実。
● 乾式DSGクラッチは“消耗品”
- マニュアル車のクラッチと同様、摩擦で動力をつなぐため、半クラが多い場面ほど消耗が早い。
- 発進時にアクセルをガバッと踏む乗り方だと、クラッチへの負担増 → ジャダーが出やすくなる。
- Stop&Goが多い街乗り中心だと、やはり摩耗も早い。
3. クラッチ交換に挑む! 7速乾式DSGの構造
● 7速乾式DSGは3つの要素で構成
- クラッチ(K1 / K2の2組)
- メカトロ(油圧&電子制御部品)
- マニュアルギアボックス
- メカトロが油圧ソレノイドでクラッチを瞬時に繋いだり切ったりしながら、次のギアをあらかじめ待機 → シームレスな変速を可能にしている。
● 第一世代(Gen.1)と第二世代(Gen.2)がある
- 2011年あたりで設計変更され、クラッチのレバー形状やシムの形が異なる。
- 純正部品とOEM(LUK製)の違いはほぼ無く、実際はLUKロゴが入っている純正品も多数。
4. 交換作業の流れとポイント
注意:特殊工具が必要なため、DIYはほぼ不可能。専門店に任せることを強く推奨します。
(1)ミッションを下ろす
- 車体からDSGミッションを取り外し、作業台へ。
- メカトロ(コントロールユニット)を取り外して、クラッチ部にアクセスできるようにする。
(2)クラッチ本体の取り外し
- Cクリップや固定リングを外し、専用SST(特殊工具)でクラッチ(K1 / K2)を引き抜く。
- 中はクラッチダストで汚れていることも多く、“消耗品”であることを再確認。
(3)シム調整(ここが最大の難所)
- クラッチ交換時、K1/K2それぞれに対応するシム(厚み違い)を調整し、ガタつき(隙間)を最適化する必要がある。
- ディーラーのマニュアルでは計算式を使うが、社外キットにはシム一式が同梱されている場合も。
- シムの厚さを変えながら、ダイヤルゲージや専用アタッチメントでクリアランスを微調整し、遊びを最小限に。
(4)組み付け~最終調整
- 新クラッチを正規トルクで固定。Cクリップなどを確実にはめ込む。
- ミッション搭載後は、VCDSなどの診断機で“基本調整を行い、DSGが自動でクラッチの当たりを学習 → 試運転で完了。
5. DSGクラッチを長持ちさせるコツ
- 発進時はゆっくり目に
- いきなり急発進しない → 半クラを多用しにくくなる。
- Stop&Goを減らす
- 都市部の渋滞ばかりだと劣化が早い。オートホールド機能を活用し、不要なクリープを避けると◎。
- 消耗品と割り切って定期的に点検
- 10万km前後での交換をひとつの目安に。
- 「昔と比べて発進時に振動が増えた」「坂道発進が苦手になった」と感じたら専門店へ相談。
6. 乾式DSGのオイル交換はどうする?
- 乾式DSG(DQ200)に入っているのは、あくまでギア部を潤滑するオイル(トランスミッションオイル)。
- 湿式DSGのように、クラッチが浸っているオイルではないため、ディーラーでは“基本無交換”を謳う場合も多い。
- とはいえ、トランスミッションオイルを交換するとシフトフィーリングが向上することもあるので、気になる方はやってみる価値あり。
7. “裏ワザ”!? 水をかけて洗う方法
あくまで自己責任&推奨はしません。
- 乾式クラッチなので、エンジン稼働中に上部のサービスホール等から水を流し、クラッチのダストを洗い流すと、ジャダーが一時的に改善するケースも。
- ただし、外に真っ黒な水が飛び散る・完全に効果が得られない場合も多い → リスクが高いので基本的には非推奨。
8. まとめ
- 7速乾式DSGのジャダー原因の大部分はクラッチ摩耗。
- DIY難易度は非常に高く、特殊工具・シム調整・基本調整の知識が必須 → 専門店での作業推奨。
- 乗り方次第でクラッチ寿命は大きく変わる。ゆっくり発進・オートホールド活用などの工夫で負担を減らそう。
- 「それでも発進時のガタガタが改善しない…」場合は、早めに点検&交換を検討するのが得策です。
★ ジャダー・DSGに関するお問い合わせはお任せ!
ナイルメカチャンネルでは、VW・アウディ車のDSG整備やクラッチ交換に多数の実績あり。
「ジャダーが出始めた」「ミッション不調かもしれない」など気になる症状があれば、ぜひ公式LINEやホームページからご相談ください。
あなたの愛車を、快適なシフトフィールに蘇らせるサポートをいたします!
チャンネル登録・ブログのブックマークもよろしくお願いします!
これからもナイルメカチャンネルでは、VW・アウディを中心に整備・カスタム情報を発信していきます。
参考動画:ナイルメカチャンネル「乾式7速DSGクラッチ交換」
関連記事:乾式7速DSG(DQ200)クラッチの構造と交換費用|ジャダー症状と長持ちのコツ
▼ナイルプラスのサービス詳細▼